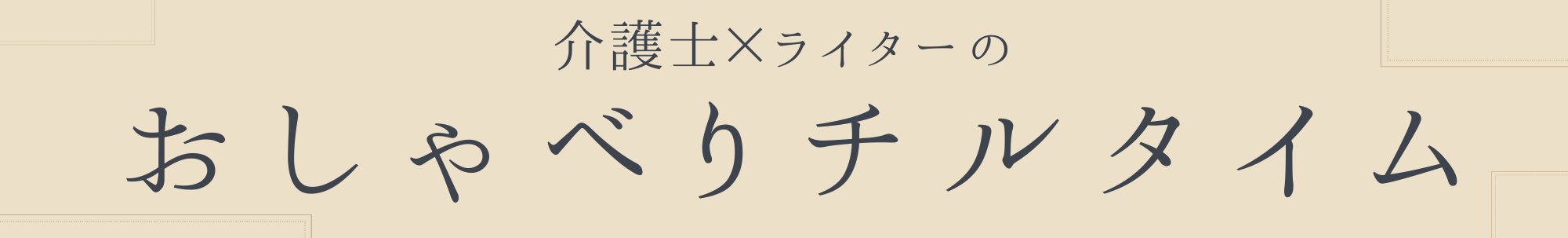介護の現場において、排泄介助は欠かせない支援のひとつです。
しかし利用者様にとっては、誰かに手助けを受けること自体が「恥ずかしい」「申し訳ない」と感じやすい場面でもあります。
“排泄は人の尊厳に直結する行為”だからこそ、介護士の寄り添い方や工夫が非常に重要です。
この記事では、介護現場で実際に役立つ「恥ずかしさを和らげるための工夫」を3つ紹介します。
介護士の方はもちろん、ご家族で介護を担っている方にも、少しでも安心につながるヒントになれば幸いです。
なぜ排泄介助で「恥ずかしさ」が生まれるのか
 介護の仕事を始めて5年になりますが、排泄介助ほど利用者様の心の繊細さを感じる場面はありません。
介護の仕事を始めて5年になりますが、排泄介助ほど利用者様の心の繊細さを感じる場面はありません。
排泄は人間にとって最もプライベートな行為であり、この支援に携わる中で、利用者様が抱く「恥ずかしさ」には深い理由があることを学んできました。
プライベート空間への他者の介入による心理的負担
この5年間、多くの利用者様と関わるなかで、排泄介助の難しさを実感してきました。
私たちは子どもの頃から「一人でトイレに行けると立派だね」と褒められ、自立を大切にしながら成長していきます。
けれども、大人になってからは身体の変化や病気によって、そのトイレにさえ誰かの助けを必要とすることがありますよね。
そうしたときに、利用者様が抱く「人に頼りたくない」「できれば一人でしたい」という複雑な思いにどう応えられるか、いつも考える日々です。
- 他の人に体を見られることへの自然な抵抗感
- 普段は人に見せない部分を露出することへの羞恥心
- 一人でゆっくり過ごしたいプライベートな時間を共有することへの戸惑い
自立性の喪失から生まれる複雑な感情
介護の現場で働き始めてから気づいたのは、利用者様の「申し訳ない」という気持ちの深さです。
これまで当たり前にできていたことができなくなる——その現実を受け入れることの辛さを、日々目の当たりにしています。
- 「お世話になって申し訳ない」という強い罪悪感
- 自分の思うように体が動かない悔しさ
- 人に頼らざるを得ない状況への複雑な思い
方法1|声かけの工夫で安心感を与える
 排泄介助の場面では、利用者様が「恥ずかしい」「迷惑をかけている」と感じることが少なくありません。
排泄介助の場面では、利用者様が「恥ずかしい」「迷惑をかけている」と感じることが少なくありません。
その不安や緊張を和らげるために、介護士の声かけは大きな役割を果たします。
ここでは、実際の介護現場で意識したいポイントを整理して解説します。
事前の声かけが不安を減らす
介助に入る際、いきなり身体に触れるのではなく、必ず一言「今からお手伝いしますね」と声をかけることが基本です。
これは、利用者様にとって「次に何が起こるか分からない」という不安を取り除く効果があります。
例えば、
-
「これから移動をお手伝いしますね」
-
「服を整えるので少し体を傾けてくださいね」
といった予告を添えるだけで、安心感がぐっと高まります。
トーンや言葉遣いに注意する
同じ言葉でも、言い方や表情によって受け取り方は変わります。
事務的に短く伝えるのではなく、落ち着いたトーンで柔らかく話すことで「信頼できる」と感じてもらいやすくなります。
逆に、早口や強い口調は「急かされている」「拒否されている」と誤解を招くことがあるため注意が必要です。
介護士の言葉は、利用者にとって「安心のサイン」となるのです。
例えば、
- 「そろそろトイレに行きましょうか。立ち上がるときは、ゆっくりで大丈夫ですよ」
- 「ズボンを整えますね。少し腰を浮かせてもらえますか?」
どちらの声かけも、利用者様の尊厳を守りながら安心して介助を受けてもらえる効果があります。
共感よりも「安心」を伝える
「恥ずかしいですよね」と共感する言葉は、一見優しそうに見えますが、利用者様の羞恥心を強調してしまう可能性があります。
そのため、
-
「できるところはご自身で、難しいところはこちらでお手伝いしますね」
-
「何か不安なことがあれば、遠慮なく言ってください」
という声かけをすると、利用者様は「自分にできることを尊重してもらえる安心」と「気持ちを受け止めてもらえる信頼感」によって、介助をより前向きに受け入れられるのです。
大切なのは、「恥ずかしさ」ではなく「安心感」に意識を向けてもらうことです。
方法2|環境づくりでプライバシーを守る
 周囲の環境は、利用者様の安心感に直結します。
周囲の環境は、利用者様の安心感に直結します。
排泄介助の場面では「見られているかもしれない」という不安が羞恥心を強めてしまうため、介護士が環境を整えることが非常に重要です。
視線を遮る工夫で安心感を高める
カーテンやパーテーションを用いて仕切ることで、他の利用者やスタッフからの視線を遮ることができます。
たとえ短時間の介助であっても「周囲から見えていない」と感じられるだけで、利用者の安心感は大きく変わります。
人の出入りを最小限にする
介助中にスタッフが頻繁に出入りすると、利用者は「多くの人に見られている」と感じやすくなります。
人の動きが少ない時間帯を選ぶ、必要のない出入りを避けるなど、周囲の配慮が大切です。
特に夜間や静かな時間帯は、利用者様にとってリラックスしやすい環境といえます。
尊厳を守るために介護士が率先する
環境調整は誰かがやってくれるものではなく、介護士自身が率先して取り組むべき姿勢です。
「見られたくない」という気持ちに寄り添いながら環境を整えることは、利用者様の尊厳を守る行為そのもの。
小さな工夫の積み重ねが、信頼関係の構築につながります。
このように、環境づくり=プライバシーの確保=尊厳保持という視点を持つことで、排泄介助はより安心感のあるケアに変わります。
環境づくりのNG例
以下に「やってしまいがちな排泄介助の環境づくり」をまとめました。
実際に働いている現場の環境はどうか、を見直すきっかけになれば幸いです。
-
カーテンを開けたまま、他の利用者様から見える場所で介助を行ってしまう
-
扉が開いており、スタッフや利用者様が頻繁に通りかかる
-
静かな環境に配慮せず、雑音が多い中で介助をしている
-
介護士が無言で作業を進め、利用者様に「見られているかも」と不安を残す
方法3|利用者様の「できること」を尊重する
 すべてを介助するのではなく、利用者様が自分でできる部分は尊重することも大切です。
すべてを介助するのではなく、利用者様が自分でできる部分は尊重することも大切です。
たとえば、下衣の上げ下ろしや体の移動を少しでも自分で行えるなら、その動作を見守るだけに留めます。
自分でできる範囲を維持することは、自立支援の観点からも有効であり、恥ずかしさの軽減にもつながります。
介護士が「やってあげる人」ではなく「支える人」という姿勢で接することで、利用者様の気持ちはぐっと軽くなるのです。
自立を尊重することの意味
利用者様が「自分でできる」と感じることは、日常生活における自尊心や自信を保つことにつながります。
すべてを代わりに行うと便利に見えますが、利用者様にとっては「できない人」という意識を強めてしまう可能性があります。
小さな動作でも自分の力でできたという体験は、生活への意欲を高め、介助を受け入れる心の余裕にもつながります。
必要最小限の支援を意識する
介助は「全て代行する」のではなく、あくまで「足りない部分を補う」ことが基本です。
-
自分で立ち上がれる方には、転倒を防ぐための見守りだけを行う
-
衣服の一部を整える動作だけをサポートする
このように必要最小限にとどめることで、利用者様の主体性が守られます。
心理的負担を軽くする効果
「自分でできることは任せてもらえている」と感じると、利用者様は「迷惑をかけていない」と安心し、羞恥心が和らぎます。
逆に、全てを介助されると「無力感」や「申し訳なさ」が強まり、心理的負担が大きくなることがあります。
そのため、介護士は身体的な支援だけでなく、利用者様の心の状態にも目を向けながら関わることが大切です。
見落としがちな不適切介助の例
ここからは、実際の現場でついやってしまいがちなNG例をご紹介します。
だめではないけど「不適切」なケアは意外と多く、気付かないケースも少なくありません。
ぜひご自分の日頃のケアと照らし合わせてみてください。
-
過剰に手を貸してしまう
➡「転ばないように」と思って、利用者様ができる動作も先に手を出してしまう。
→ 利用者様は「自分にはできない」と思い込みやすく、自立心を削がれる。 -
スピーディーに終わらせることを優先
➡ 利用者様を気遣って「早く済ませてあげよう」と動作を急ぐ。
→ 利用者様は「迷惑をかけている」と感じ、罪悪感が強くなる。 -
介助中に別のスタッフと会話する
➡ 業務連絡を兼ねて他の職員と会話しながら介助を行う。
→ 利用者様は「置き去りにされている」「恥ずかしさを無視されている」と感じる。 -
明るすぎる照明の下で介助する
➡ 清潔保持を意識して照明を強めにする。
→ 利用者様にとっては「余計に見られている感覚」が強まり、羞恥心が増す。 - 「ちょっと待っててください」と放置してしまう
➡ 他の対応で手が離せず、介助途中でそのまま離れる。
→ 利用者様は無防備な状態で待たされ、不安や羞恥心が強まる。
まとめ
排泄介助に伴う「恥ずかしさ」は、利用者様が抱える自然な感情です。
しかし、介護士の声かけや環境づくり、自立支援の姿勢によって、その負担を和らげることができます。
介護の現場で大切なのは、単なる「介助」ではなく、利用者様の尊厳を守り、安心して生活できる環境を整えることです。
小さな気配りの積み重ねが、利用者様との信頼関係を築く大きな力となるのではないでしょうか。
みなさんも、排泄介助に入るときに工夫していること・意識していることなどがあればぜひ教えてください。